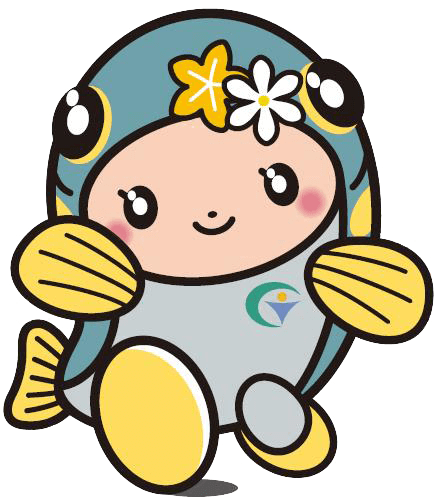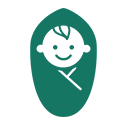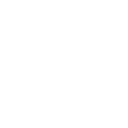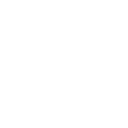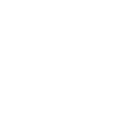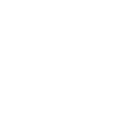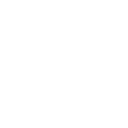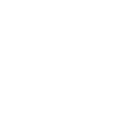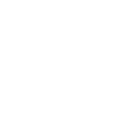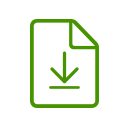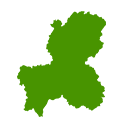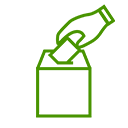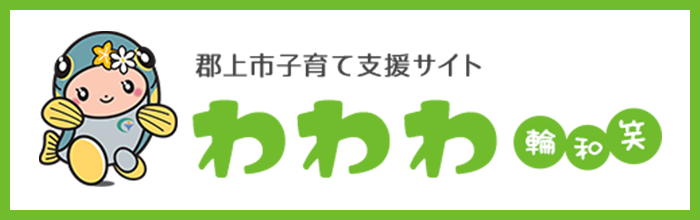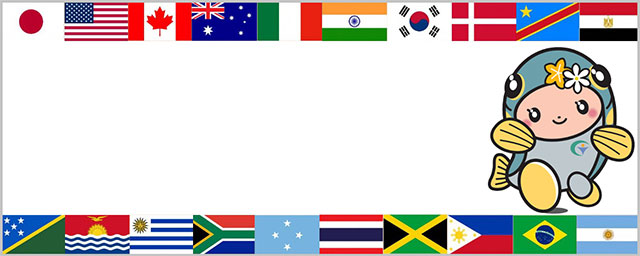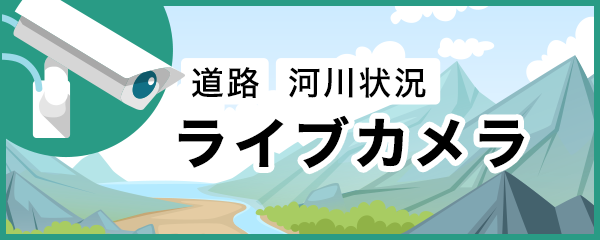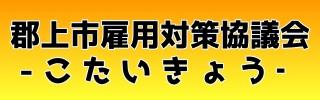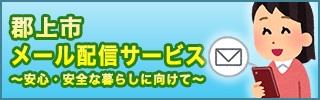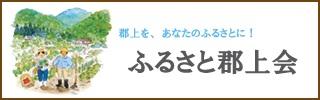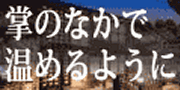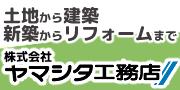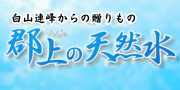白山信仰のはじまり

石川・福井・岐阜県境にまたがる白山連峰(2,702m)は、古来より山岳信仰の対象となった霊山のひとつです。養老元年(717)、泰澄大師が白山に登り、神のお告げを受け、白山信仰のもとを開いたとされる伝承が「泰澄和尚伝」に記されています。白山で修業した泰澄は、美濃(岐阜県)、越前(福井県)、加賀(石川県)の三方から白山へお参りする道を開いたとされています。美濃側からお参りする拠点として、白鳥町長滝に白山中宮長滝寺を開き、「美濃馬場」とよばれました。東海地方から参拝する人たちは、まず洲原神社(美濃市)に参拝し、長良川を北上して白山中宮長滝寺、石徹白白山中居神社などをお参りして、白山山頂をめざしたとされています。
平安時代初期に始まった天台宗は、京都の延暦寺を中心に大きな勢力を持つようになりました。白山中宮長滝寺はこの延暦寺の別院となり、東海地方の信仰の中心となりました。そのため、長滝寺は、「六谷六院、神社仏閣三十がならび、衆徒三百六十坊」といわれるほど大きく栄えるようになりました。
鎌倉時代に入ると、武士が戦いの勝利などの祈願を依頼するようになり、土地や宝物が寄進され、ますます繁栄しました。その最盛は、「奥美濃の正倉院」と称されるように多くの文化財を所有し、「延年」や「花奪い」に象徴される六日祭によって、今日でもうかがい知ることができます。
郡上郡の成立
平安時代の斉衡2年(855)、美濃国武儀郡は二分立して武儀・郡上郡となったことが、「文徳実録」に記されています。郡上郡には、郡上・安郡・和良・栗垣(栗栖)の四郷が置かれました。その後、平安時代後期に荘園制が展開してくると、郷名は消え、変わって気良・山田・吉田荘が成立しました。

山岳信仰と藤原高光伝説
郡上南部には、高賀山や瓢ケ岳などの高い山が聳え、古代から霊山として、信仰されていました。平安時代、村上天皇の頃(946~967)、瓢ケ岳に鬼が住み村人を苦しめているといわれていました。時の朝廷は、藤原高光に鬼退治を命じ、この地に派遣しました。高光は自身が信仰する虚空蔵菩薩に祈願し、菩薩の助けによって鬼を退治したとされています。その後、高光は鬼などの厄災を払うため、高賀山、瓢ケ岳などのふもとに六つの神社を開き、虚空蔵菩薩を祀りました。
この六つの神社(六社)に修験者が互いに行き来して、修行を行うようになりました。後に一般の信者にも広がり、六社めぐりが盛んに行われるようになりました。郡上市には六社のうち那比本宮神社、那比新宮神社、星宮神社の三社があります。