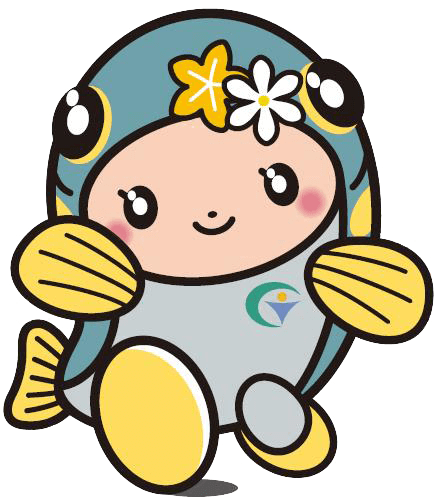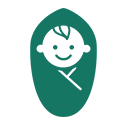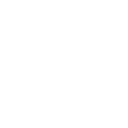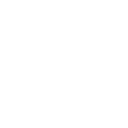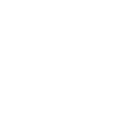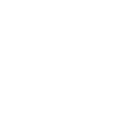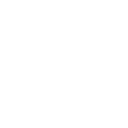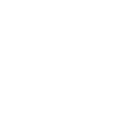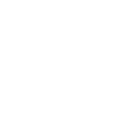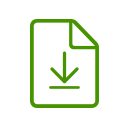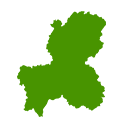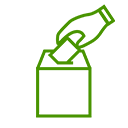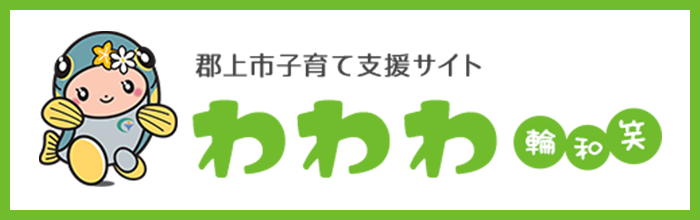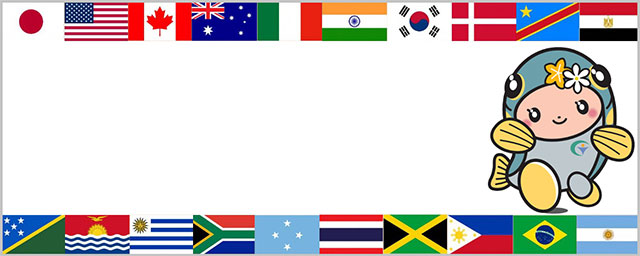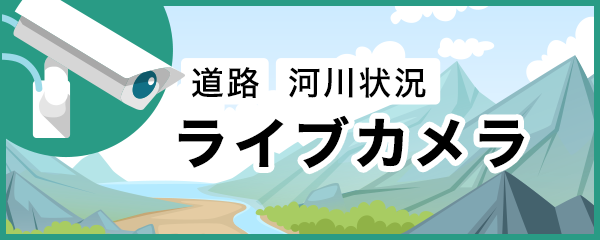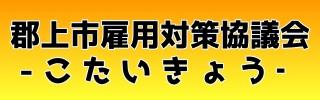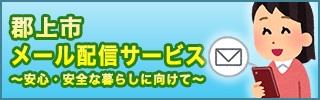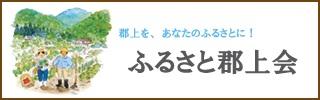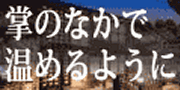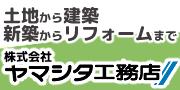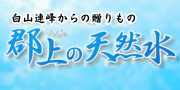施政方針は、令和7年度の郡上市における市政運営に関する所信と基本的施策であり、令和7年第1回郡上市議会定例会において市長より表明したものです。
冒頭あいさつ
本日、「令和7年第1回郡上市議会定例会」を招集いたしましたところ、議員各位には、ご参集いただき誠にありがとうございます。今定例会の開会に当たり、ご審議いただきます諸議案の説明に先立ち、市政運営の基本的な考え方と新年度当初予算の編成方針、また、この予算に盛り込みました主要な施策や事業等についてご説明申し上げ、議員各位並びに市民の皆様方のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。
市政運営の基本方針
はじめに、市政運営の基本方針についてご説明申し上げます。
80年前、我が国は終戦を迎え、先の大戦で破壊され荒廃した国土を復興すべくスタートラインに立ちました。国民は豊かになろうと朝早くから深夜に至るまで必死に働きました。その結果、平和が訪れ、生活レベルも上がってきたため第一次ベビーブームとなり、日本の人口は爆発的に増えることとなりました。そして、多くの中学卒業生が地方から大都会へと送り出され、金の卵ともてはやされました。こういった多くの人口を支えるために都市間を結ぶ高速道路や新幹線、飛行場などのインフラが整備され、国民の支え合いによる健康保険制度が創設され、高度医療を提供する大病院がいくつも開設されることとなりました。生活用水としての山水は蛇口をひねればいつでも清潔な水が出る上水道となり、汲み取り式便所は水洗トイレとなったのです。こういった戦後システムは、右肩上がりの経済と増加する労働人口によって支えられてきましたが、社会構造が大きく変化するに伴い、国民は政府からの補助金、交付金の生活に慣れてしまい、問題と対峙したときに自分たちで考えることをやめて、すぐに政府や地方自治体などの行政府に依存する傾向が強くなってしまったのではないでしょうか。
郡上市は、昨年3月に合併から20年を迎えました。7つの町村が1つになり約49,000人の新しいふるさとが誕生したとき、誰もが未来の郡上に期待したことでしょう。それが20年で約4分の1の人口が減少し約38,000人となっています。また、人口構成も変化し、多くの団塊世代の方々が後期高齢者となる一方で、社会を担い中核となる生産年齢人口は減少しています。とりわけ郡上市の将来を背負って立っていただかなければならない若い世代の人口は激減し、昨年郡上で生まれた子どもは151人でした。こうした状況のなかで今後の郡上市を支えていくには一体どうしたらいいのでしょう。私は、こう考えます。年配の皆様には、健康に十分ご留意いただき、医療費の抑制に努めていただくことが重要です。また元気なアクティブシニアの皆様には、現役世代を助けて社会を支えていただきたいと思います。若い皆様は、多くの年配の世代が一生懸命働いて、この「ふるさと郡上」をつくってきてくださったことに感謝の念を持ち、これからも敬い大切にしていってください。男女共同参画社会の中で、性別による隔てなく、一人ひとりが大切な自分であると認識するとともに、郡上を支える重要なひとりであることを自覚していただき、各分野で活躍していただくことを期待いたします。このように、世代や性別に関わらず、市民全員の協力なくして今後の郡上市の再生はないと思います。
私は、昨年の4月に郡上市長を拝命し、未来に向けた郡上市づくりに取り組ませていただいています。この間、副市長2人体制によるトップマネジメントの強化、私の思いを込めたオムツのサブスクリプションに係る事業等、関係条例の改正や補正予算をお認めいただきました。とりわけ副市長2人体制については、現在、両副市長で管轄する業務を分担し、各部署からの課題に迅速に対応するとともに、今回の予算編成をはじめ重要な事項は、市長、両副市長で常に情報と判断を共有し意思決定のスピードを速めており、有効に機能しています。一方、既決予算であった偕楽園の新築移転、美並の工業団地造成、そしてゴミ処理施設であるクリーンセンターなどの大事業については、郡上の将来にとって大きな足枷になるとの考えから、方針見直しのための予算凍結を断行させていただいたところです。これらは、議会に対してもこれまでの経過をすべてお話して、これまでの決定プロセスの中で十分説明しきれていなかったこともお詫びした次第です。
こういった一年を経験して、先の選挙の際に皆様にお話ししてきた「現場主義」を実践するために、高校へ出かけたり、健康体操の現場に伺ったりするなど、多くの市民の皆様とタウンミーティングを行ってまいりました。計26回、534人の方々と事前に質問を出していただくこともせず、回答を用意することもなく、シナリオ無しの話し合いを行ったところです。そして、話し合いを重ねるなかで、令和7年度の予算編成にあたって、この20年間の総点検を行い、ゼロベースに戻す作業、つまりリセットをする必要があると考えました。合併前の町村時代に始まり、その後も効果の検証結果を見直しに反映していない事業はないか。終期を決めることなく、拡大の一途をたどった事業はないか。人口減少が起こっている中、本当に既存の事業を継続することが可能なのか。もっと効果のある事業への転換はできないのかということに思いを巡らしました。
このような考えを根底に置きながら、私は、「命を守る」、「郡上をまもる」、「若者の未来を守る」を市政運営の基本方針とし、郡上市の持続可能な発展を推進していきます。特に、若者人口が減少している状況を食い止め、次の郡上市を託す若い世代から支持していただける郡上市につながる施策を推進し、消滅可能性自治体からの脱却に向けて挑戦していきます。
予算編成方針・総予算額
続きまして、予算編成方針についてご説明申し上げます。
現在、郡上市には、災害などの不測の事態や年度間の財源の不均衡に備えるための「貯金」に相当する財政調整基金がありますが、今回の大雪に伴う除雪経費の増大により約4億7千万円となる見込みです。合併後、一番多かったときには約43億円ありましたが、減少の一途をたどり、私が市長を拝命した約1年前には15億円となっており、その他の特別目的で貯めていた基金も現在は大きく減少しています。また、皆様の命を守る医療機関である2つの公立病院は、年間に10億円を超える資金不足となっており、今後の資金繰りはもう待ったなしの状態です。
このような財政状況を考慮し、12億7千万円もの基金を充てた令和6年度の予算編成を見直し、令和7年度は、7億1千万円の基金充当にとどめた緊縮的な予算編成としました。
先ほども申し上げましたように、先人たちが知恵を出し、合併前からそれぞれの町村で大変苦労して進めてきた事業に関しても、尊重はしながらも今一度見直すときが来たと考えています。このため、これまでの予算のあり方を抜本的に見直し、指定管理者制度による施設管理運営経費や文化的事業をはじめ、若者、年配の方など、世代を問わずその役目を終えた事業などは、今回思い切って縮小させていただきました。見直した事業の中には、補助金・交付金の減額や廃止など、個人や団体の皆様に直接影響が及ぶものもございます。急な話ではないか、数年後までに徐々に段階を踏んで削減する方法はなかったのか等、お叱りを受けることも承知しています。ここで皆様が会社を経営しておられると仮定してください。経営が行き詰っている中で事業見直しを進めるとき、時間をかけて段階的に予算を削減するとか、何年かかけてゆっくり調整することなどできはしません。今回の予算編成は、そういった状況のなかで行ってきたことをご理解ください。
しかし、全てが緊縮というわけではございません。「若い世代へのシフト」を掲げて、若者世代が郡上へ戻ってきてくれることを期待し、子育てに優しいまち郡上を自他共に認めていけるような政策も考えてあります。また、高齢者の皆様にもご負担をおかけするばかりではなく、本当にお困りの方々に対する政策も用意いたしました。加えて、今後のことを少し述べると、郡上市がもつ最大の資産である広大な森林の有効活用も考えています。この森林をただ管理し、立木だけを売却するのではなく、適切な森林管理による二酸化炭素等の吸収量を「クレジット」として国が認証する、いわゆる「J‐クレジット制度」を最大限活用し、企業等へ売却することで独自財源として活用していく施策を進めていきます。
市民の皆様には、「私たちだけ損をした」とか、「私たちの地区だけ何もしてもらっていない」などおっしゃることなく、皆がこの人口減少社会の中で我慢することはお互い我慢する。この我慢は、将来、郡上の子がまた戻ってきてくれて、素晴らしいふるさと郡上をつくっていってくれることに繋がるのだという希望のなかで、今、自分たちにできることは何かを考えるチャンスが来たのだと、前向きに捉えていただきたいと思います。
このような視点に立って、若者はもちろんのこと、誰もが元気に安心して幸せに暮らすことができる郡上の未来を目指した内容の予算編成となっています。
続いて、予算総額について説明します。一般会計の歳入では、市税は、景気の回復傾向による法人市民税や定額減税の終了による個人市民税の増加などにより、前年度比6%増の50億784万円を見込んでいます。加えて、ふるさと納税の寄附額拡大による、3億8千万円の歳入を計上しています。
歳出では、廃止・縮小、新規事業を盛り込んだうえで、昨今の物価高騰の影響なども加味した結果、前年度の6月補正後の予算(肉付け後予算)比で0.3%のアップとなる、8,720万円増の277億8,800万円の予算としました。
特別会計は、113億4,414万円(0.6%、6,294万円の増)、企業会計は、116億1,771万円(0.4%、4,295万円の増)、総合計では、507億4,986万円(0.4%、1億9,308万円の増)としました。
分野別施策
続きまして、「第2次郡上市総合計画」の柱立てに沿って、7つの分野別施策における項目ごとの主な内容をご説明いたします。
1.産業・雇用(地域資源を活かして産業を育てるまち)
最初に1つ目の柱である『産業・雇用』についてであります。
農業に関する今後の大きな課題は、農地や法面等の保全管理に関することだと考えています。現在、市では地域の農業の未来を示す「地域計画」の策定を進めています。策定後は、この計画を推進し、中間管理機構等を活用しながら農地の集積を図ることで、地域の農業をしっかりと守ります。また、地域計画に基づいた農地維持のためには、認定農業者を含めた担い手の皆様は重要な存在であると考えます。認定農業者への支援を進めるとともに、国県の制度を活用しながらJA等と連携の中で新規就農者の育成を促進します。もう一つには、多くの農地を守っている兼業農家や非農家の方々を含めた協力をどう築いていくかを、真剣に考えなければなりません。地域によっては、圃場が小さく集積が困難な地域もあることから、隣接する森林や周辺環境も含めて、移住者や若い世代が維持管理に携わっていただき、これに対して給付制度による直接支援を行うことを国、県に対しても要望していきます。
また、農地等の再基盤整備が今後の不可欠なステップと考えます。昭和・平成の時代に整備した水路等基盤の老朽化、大型機械が効率よく作業できる規格の農地の再整備などの課題に対し、市民の皆様と協力しながら進めていきます。こうしたことは、一律に行うのではなく、やる気のある地域から順次進める方針で、みんなで力を合わせて集積や整備を進めてまいります。
新知事は、有機農業や耕畜連携などについて提唱されています。農業には、地域の特性を活かし、新たな付加価値を創出する方向性も求められているため、郡上市でも量だけでなく品質にも目を向けた取組みを検討してまいります。
加えて、温暖化の影響が顕著に現れ、昨年の郡上市南部地域における水稲は、約77%が二等米以下という厳しい結果でありました。この現状に対応するため、高温に強い品種や栽培方法の研究を東海農政局や県、JAと連携して進めていきます。また、他産地と比べ標高の高い優位性を活かして、夏だいこんや夏秋トマトなどの特産作物の生産振興に一層取り組んでいきます。
このほか、進学した郡上の子が卒業後に地元に戻り就農する、また、他地域から農業を志す方に郡上市を選んでいただける仕組み、外国人労働者の受け入れのための支援や、サポートを検討してまいります。
こうした農業施策に必要な支援や補助を継続していきますが、農業関係者の皆様には、過度に補助金に頼らない持続可能な農業を目指し、力強い郡上の農業を共につくり上げていただきたいと思います。
次に畜産についてです。畜産分野では後継者の確保が求められており、これに対する具体的な対策が不可欠です。また、近年、インバウンド需要の増加に伴い、飛騨牛への関心が高まっています。高山市などではふるさと納税の返礼品としても人気があるとのことです。このような状況のなかで、郡上市としても商機を見出していくことが考えられます。本市においても、良質な飛騨牛の生産を支援し、郡上で生産された飛騨牛をふるさと納税の返礼品として活用を推進するなど、安定した収入を確保できる環境を整え、家業を継続しようというマインドを醸成してまいります。
これまでは、農家一軒一軒に対して光熱費や資材費の直接給付を行ってきましたが、今後は畜産振興全体を見据えた支援が必要です。具体的には、耕畜連携のために市とJAなどが連携し、排泄物を肥料化するプラントの設置・強化に向けた協議を進め、生産者間の協力体制を構築していきます。このような取組みにより、個々の農家だけでなく、地域としての強さを発揮できる土壌を整えてまいります。さらに、現場の声を大切にし、職員はもちろん私自身も担い手や若手後継者との対話を通じて、彼らが抱える課題を共に探求し、解決策を模索していくつもりです。
続いて、森林・林業についてです。郡上市は、令和6年度見込額で3億2,649万2千円という多くの森林環境譲与税を受け取っています。この資金を活用し、私たちは森林資源の多様な可能性を追求してまいります。現在、市では、先人が植林してきた9万ヘクタールの森林が伐期を迎えていることから、皆伐再造林事業を拡充し、住宅建材やバイオマス資源への供給も含め有効活用を図るとともに、新知事が路網の整備の必要性を提唱されていることを踏まえ、歩調を合わせて森林の基盤整備に取り組むことで、木材の生産量を今後増大させてまいります。
その一方で、山林への関心が薄まり、境界の把握が困難になってきていることに懸念を抱いています。特に、個人で山林を管理していく難しさが顕在化してきているため、地域の皆様と協力しながら所有権の明確化に努めていくとともに、森林所有者合意のもと、施業する団地の外周だけを境界明確化し、市等で管理や施業を進める「スーパー入会林」などの新しい考え方を取り入れ、森林資源の増産、集積を進めることにも力を入れます。さらに、新知事が提唱する、木材を高圧で圧縮して作るバイオコークスの利用方法についても、県と共に実現可能性を調査し、準備を進めていきます。これにより、森林資源の新たな利用価値を見出し、地域経済の活性化を図ります。
また、獣害対策についても、猟友会などとも連携しながら、被害の軽減に向けた取組みを強化します。現在、植林地ではネットやツリーシェルターを活用した被害対策が行われていますが、降雪による倒伏被害を鑑みると、より柔軟で実効性のある新たな対策の研究も必要です。捕獲手段の充実を図り、その他の防除も含めた総合的な対策を講じて持続可能な森林管理に努めてまいります。
次に、商工についてです。商工活動を活性化するためには、次世代の担い手である若い世代の力が必要不可欠です。若者が自ら考えたアイデアを実現し、活躍できる環境を整えることが、地域全体の発展につながります。また、地域経済の成長には、高速道路をはじめとする交通インフラを最大限活用していく必要があります。このため、東海北陸自動車道や中部縦貫自動車道などの高規格道路の整備に合わせ、結節点となる本市内において、商業活動をより活発にするためのイベントや交流の場を設けていきたいと考えています。例えば、メガマルシェの開催などにより地域内のビジネスチャンスを拡大し、商工業の振興を図っていきます。
これまで、市では学校を卒業し新規に就職する若者に対してお祝い金を支給してきましたが、今後は事業所への給付に切り替え、事業所が行うリクルート活動の充実や、働きやすい職場環境の整備などについて支援を行います。これにより、若者が新たに就職することで、新規就労が少ない現状を打破し、地域の雇用状況も改善されることを期待しています。
また、これはお願いですが、親御さんたちにも、郡上市には多くの求人があることをしっかりと理解していただき、地域の若者が「職場がない」と誤解しないよう、ぜひ正しい情報を発信しいただきたいと思います。そのために、親世代にも求人情報などを共有していきたいと考えています。
続いて、観光施策についてです。観光面では、郡上市観光連盟(DMO)がSNSなどのWEBメディアを活用した情報発信やマーケティングに取り組まれており、地域の観光振興に大きく貢献されています。こうした取組みは郡上市の魅力を国内外に広める重要な手段であるため、今後も、地域の発信力を最大限に高め、国内外へ情報を届ける活動を継続して実施いたします。
現在、市では多くの雪が降り積もっていますが、これを活かす形でスノーリゾート形成促進計画の実現に向け引き続き取組みを推進してまいります。例えば、近隣の一大観光地である高山市などと共同で、郡上市のスキー場へ外国のお客様をお招きする取組みを充実していくことも検討したいと考えています。そして、こうしたことも踏まえ、オーストラリアで開催されるスノー・トラベル・エキスポ2025にてトップセールスを実施することで、特に豪州、ひいては海外市場へのアプローチを強化したいと考えています。さらに、郡上市が誇るアウトドアコンテンツや、4つの国重要無形民俗文化財を含めた「郡上のおどり」など、多くの文化・芸能を観光資源として捉え、地域の魅力向上・通年観光に努めていきます。これらにより、日置前市長が提唱された「観光立市郡上」の実現に向け、力強く歩みを進めてまいります。
2.環境・防災・社会基盤(美しい水と緑を守り、暮らしの基盤が整う共生のまち)
続きまして、2つ目の柱である『環境・防災・社会基盤』についてであります。
美しい水と自然に囲まれた郡上市は、市民にとっての誇りであるとともに、海外からの観光客にも大きくアピールするポイントとなります。そのため、地域の成長戦略として引き続き「脱炭素社会郡上」の実現を目指して取り組みます。市内の公共施設の多くでLED化を進めることは、脱炭素社会郡上実現に向けた市の責務であると考えています。まずは、庁舎施設照明の計画的なLED化により、脱炭素の推進とランニングコストの削減に取り組みます。なお、郡上市を観光立市かつゼロカーボンのまちとして発展させるためには、市民の皆様の意識向上も必要です。家庭においても、それぞれがゼロカーボン社会の実現に向けて行動することが求められます。この意識が、環境保全に繋がると信じていますのでご協力をお願い申し上げます。
環境保全と廃棄物対策においても、市民の皆様の意識が重要です。生ごみを減らし、処理場への負荷を軽減するためには、生ごみの水切りやコンポスト容器での堆肥化、生ごみ処理機での減量化が有効です。これを進めるための具体的な取組みとして、ごみ減量化機器の購入費用に対する補助を行い、各家庭での利用を促進します。環境保全の基本は、皆様一人ひとりの行動にかかっています。より良い地域社会にしていくため、自分たちが主体となって何ができるのかを考え、実践していただきたいと思います。
さらに、クリーンセンターの更新についても触れさせていただきます。新設の場合には、建設費用と20年間のランニングコストを含めて約220億円という大きな費用が試算されましたが、既存施設の延命化や広域的な処理の方法を模索することで、コストを大きく削減できる可能性があると考えています。持続可能な施設のあり方を研究し、最適な解決策を見出していきます。
次に、水道事業についてです。郡上市では、中長期的な水道事業経営の基本計画である「郡上市水道事業ビジョン」を定め、市民の皆様に安全な水を安定的に供給するよう努めています。しかしながら、現在の水道事業は、料金回収率が約60%と低く、一般会計からの繰入に依存した経営が続いている状況です。平成30年度に水道法が改正となった際、水道料金が適正かどうかを検証し、3~5年毎の適正な時期に見直すことが規定されましたが、過去20年間水道料金の改定を行うことなく現在に至っています。また、大規模地震の発生が懸念されるなか、老朽化した水道管路の更新は必要急務である一方で、管路更新には膨大な費用を要することも課題となっています。この財源として補助金を最大限活用していくことが必要であり、水道事業を管轄する国土交通省からの補助金の採択要件を満たすためには、水道料金を全国平均以上にする必要がありますが、令和6年度における本市の10㎥当たりの水道料金は、1,320円と全国平均の1,604円を下回っている状況です。つまり、大変安い料金で皆様に水を供給してきたことになります。こうしたことから、今回、郡上市水道事業ビジョンを確実に実行し水道料金の見直しを行います。具体的には、一般家庭の水道の基本料金を、お風呂約5杯分に相当する1㎥あたり40円引き上げることを考えています。この料金改定は、郡上の水道サービスを維持し、持続可能な運営を実現するには不可欠な措置であるとご理解をお願い申し上げます。
次に、消防・防災についてです。現在、郡上市では、面積や人口がほぼ同等の他自治体に比べて消防職員が不足しています。各種災害から市民の生命や財産を守り、長期的に安定した消防力を維持するため、他の自治体の状況を勘案しながら消防職員の増員を計画的に進めます。この消防職員増員に関して重要な点は、消防職員の活動の大半が火災出動ではなく、日常的な救急要請であるということです。今年1月の救急要請件数は198件と異常な増加を示しています。この状況を改善するためには、市民の皆様一人ひとりが救急車の適正な利用について考え、他人事ではなく自分事として捉えていただくことが重要だと考えています。
災害対策においては、引き続き防災資器材の整備に対する支援や、訓練及び研修会を開催し、自主防災組織の育成強化を図ります。また、孤立集落対策として、自主防災組織への補助金について、集落要件を緩和し補助率を見直します。
「令和6年能登半島地震」では、度重なる余震により多くの家屋が倒壊し、尊い命が失われました。国土交通省では、耐震基準を満たしていない木造家屋などの倒壊の割合が、耐震化された建物と比較して著しく高いと分析しています。本市でも、木造住宅の耐震化について支援を実施していますが、耐震が十分でない住宅にお住いの方は、地震発生後は公共施設や場合によってはご近所の耐震性が高い家屋へ避難していただく必要があると考えますので、日頃から自治会はもとより、隣近所の方々とのコミュニケーションを図り、円滑な共助体制を築いてください。また、各家庭においても、「自らの命は自ら守る」自助の精神に基づいて、水や食料を備蓄するなど有事に備えていただきますようお願い申し上げます。
次に、社会基盤の整備についてです。市では、これまでに道路や橋梁の整備・維持管理に努めてまいりました。しかし、今後は、厳しい財政状況の中で、激甚化・頻発化する自然災害、人口減少等による地域社会の変化、既存のインフラ施設の老朽化など、様々な課題に対応していかなければなりません。そのため、新たな道路・橋梁の整備はもとより、既に整備された道路施設等の維持・補修に関しても、維持管理費の適正化を図りつつ必要性を十分見極めた上で実施していきますが、今後すべての道路や橋梁をこのまま維持し続けることは困難と考えますので、各地域においても、真に必要な道路施設等についてご検討くださるようお願いいたします。また、これまでの数年間、郡上市には大きな災害はありませんでしたが、一旦、能登半島のような大規模な災害が発生した際、私たちの防災対策はまだ十分ではないと認識しております。このため、河川の護岸や砂防堰堤など大災害の未然防止のための施設整備を関係機関へ働きかけるとともに、市においても引き続き整備を推進してまいります。必要な道路整備を行いつつ、河川、砂防、治山施設の整備の充実を図り、安心安全なまちづくりを目指すことで、持続可能な地域づくりにつなげてまいります。
また、住環境の整備についてですが、市の目標は、若者が地域に戻り、住宅を建て、安心して生活できる住環境を整えることです。このため、郡上市産材の活用を図りつつ、若者の移住定住に向けた新たな住宅建築への補助制度を創設し、支援します。特に、子育て世代を支援するためにも、住宅建築に対する補助金の上限額を従来の70万円から100万円に拡充いたします。この施策により経済的負担を軽減し、地域に愛着を持って生活する若者を増やしていくことで、地域の活性化、未来を担う次世代の育成につなげてまいります。
次に、公共交通対策についてです。現在、市では路線バスや自主運行バスの運行に年間およそ2億5千万円を支出し、市民の皆様の移動手段の確保に努めています。しかしながら、人口減少などに伴って利用者が減少していることや、物価高騰などにより運行経費が増加している状況を鑑み、公共交通のあり方の抜本的な見直しに着手します。なお、見直しにあっては、公共ライドシェアの導入の可能性を含め、国の制度なども活用しながら進めてまいりたいと思いますが、市民の皆様方も、現在だけではなく将来の移動手段も含めて、地域における公共交通の必要性についてぜひ考えてください。また、長良川鉄道のあり方に関しては、皆様のご意見をお伺いしながら、私の任期である4年の間に郡上市としての具体的な方針を示していきたいと思います。なお、公共交通に関しても、市が全てを担うという考え方から、一人ひとりが自分たちの地域で何が最も使いやすいのか、また、助け合うためには何ができるのかを考えていただく機会を持ち、地域の皆様が主体となる取組みを進めていきたいと考えています。
3.健康・福祉(支えあい助け合う安心のまち)
次に、3つ目の柱である『健康・福祉』についてであります。
子育て支援の取組みとしまして、私の公約の一つであるおむつのサブスク事業については、託児所への拡充を図っていきます。また、将来を担う子どもたちのためには、現在各地域にある保育園等の老朽化対応が急務であると認識しております。特に、土砂災害の特別警戒区域に位置する明宝保育園に関しては、安全性の確保が最優先です。保育園の明宝中学校内への移転・複合化を進めることで、より安全で安心な環境を提供するとともに、学校と保育園の連携によって、地域の絆を一層強めていくことができればと考えており、この取組みを通じて、地域社会を支える基盤を築き、子どもたちが健やかに成長できる環境を整えてまいります。
続いて、高齢福祉についてです。これまで、敬老の日のお祝いとして75歳以上の方へ一律に2,000円を支給してまいりましたが、そのあり方について見直しを行います。私が子どもの頃は婦人会や自治会が中心となり、年配の方々への敬老の意を示すためにお弁当を配布したり、催し物を開催したりしていました。しかし、現在では、約8割の自治会などにおいて、商品券を配布することでお祝いに代えているのが実態です。これを踏まえ、全員への給付ではなく、本当に困っている方々に対して有意義な支援ができないかと考えました。特に、高齢者の中には車を運転できない方や、買い物、病院への移動が困難な方が多くいらっしゃいます。このような方々のための必要な施策として、生活に必要な食品等の移動販売を行う個人事業主に対する助成制度を設け、高齢者の買い物支援を強化します。このように、変化する地域社会のニーズに応じて柔軟に対応することで、真に必要な支援を実現していきたいと考えています。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
また、郡上偕楽園につきましては、ご承知のとおり水害の際に危険な位置にあり、これまでにも速やかな移転が求められてきたことから、令和3年度に移転に係る基本計画を策定し取組みを進めてまいりました。しかしながら、将来の老齢人口の推移を見据えるなか、適正な定員への見直しが重要との観点から再検討を行い、特養、養護、ショートステイのベッド数は、見直し前の計画で想定していた125床から69床へ削減することとしました。移転先につきましては、これまで申し上げてきたように、大和第一北小学校の跡地としますが、養護老人ホームの機能は旧校舎を活用する計画としており、令和10年度からの開設を目指して実施設計を進めていきます。
次に、医療・健康保険についてです。現在、市が運営する2つの公立病院では、医療従事者が熱心に患者様やそのご家族に寄り添い、質の高い医療を提供しています。私たちは、他の地域に引けを取らない高度な医療水準を確保し続けるために、医療機器の整備と更新を進めております。しかしながら、人口減少が進むなかで、経営改善だけでは解消できない構造的な赤字体質が問題となっています。予算編成方針でも申し上げましたが、年間約10億円の補填が行われている状況です。このままでは、公立病院2箇所に加え、精神科を含む3つの私立病院の現在の病床数を維持することは難しいと考えています。そこで、今後の医療提供のあり方について、従来の考えを一度リセットし、医師会と共に真剣に議論を進めながら、公立病院と民間病院との連携を模索するともに、公立2病院にあっては、持続可能な医療を提供できるよう経営の改善に取り組みます。とりわけ、郡上市民病院については、これまでの「経営強化プラン」や今後策定予定の「経営改善計画」に基づき、財務等経営状況の改善に本腰を入れていきます。また、医師の高齢化に伴い、新たに医師をどう確保していくかも重要な課題です。デイサービスや在宅での訪問医療及び介護、施設入所、入院等を一体的に考え、今後20年間、安心できる医療体制を構築することが求められます。この過程では、必ずしも容易ではない痛みを伴うこともあるでしょうが、関係者のご理解とご協力が不可欠です。また、国民健康保険に関しても、加入者数の減少により経営が厳しい状況に直面しています。郡上市では、平成30年度以降値上げを見合わせてきましたが、令和11年に県下で統一される岐阜県基準に合わせる必要があり、これに向けて段階的な国保税の引き上げを皆様にお願いせざるを得ないと考えています。
4.教育・文化・人づくり(香り高い地域文化と心豊かな人を育むまち)
次に、4つ目の柱である『教育・文化・人づくり』についてであります。
教育と文化を振興し、人づくりにつなげていくことは重要な施策です。これまでも、教育振興基本計画に基づき、多くの人材を育成してきておりますが、これからは郡上を支える人材を確実に育て、彼らが将来郡上に帰ってくる環境を整える必要があると考えています。このため、日置前市長が始められた「郡上学」を深め、親しみを持ってもらい、更に進めていく「シン・郡上学」を推進し、実践的な地域学習プログラムを充実させるなかで、郡上への愛着を育んでいきます。また、地域の人材育成と地域課題の解決のため、地域全体で子どもたちの学びや成長を支え、学校を核とした地域づくりを行う「地域学校協働活動」を推進します。地域の皆様、とりわけシニアの皆様には、シン・郡上学や地域学校協働活動に積極的に参画していただき、子どもを含めた地域の絆を深め、地域を活性化し、郡上を守っていただきたいと思います。
加えて、教育と子育てに関する新事業として、旧大和第一北小学校の体育館を再利用した木育施設、「ぎふ木遊館サテライト施設」の整備を計画しております。この施設は雨の日の遊び場を求める保護者の声に応えるものであり、地域の交流を促進する場としても機能することを目指しております。特に、今後移転する郡上偕楽園と隣接して整備することで、ご年配の方々と子どもたちとの交流を生む機会も創出したいと考えています。
学校教育では、中学生の学校給食費無償化や高校生の通学費助成を市内2校のみから市外の高校への通学費及び下宿代を対象に拡充するほか、小中学校でタブレット端末を通して心や身体の状況を早い時期から把握できるITツールを導入し、児童生徒の心身の不調に対してしっかりと対応できる取組みを行っていきます。
さらに、学校の適正規模・適正配置に関しましては、これまで市が進めてきた計画について、多くの皆様からのご意見を伺ってきました。そのなかで、美並地域の小学校統合については、地域の方々やPTAなどから統合を進めたいという強い思いが寄せられていますので、令和7年度の推進スケジュールを立て、協議を進めながら実施設計に取り組んでまいりたいと思います。今後、その他の学校の統合については、地域でご理解をいただいたところから皆様と協力しながら進めていきます。
郡上には、豊かな文化と伝統が息づいています。このたび、「白鳥の拝殿踊」が文化庁文化審議会から重要無形民俗文化財として答申されました。この他にも、郡上には3つの重要無形民俗文化財が存在し、私たちはその価値を誇りに思っております。郡上は「日本一のおどりのまち」として、踊りを中心に観光や経済の振興に取り組んでいます。子どもたちが踊りを通じて郷土愛を育む姿は、文化の保存と伝承に繋がる重要な要素です。今後も保存会と協力し、おどりのまちとしての取組みを進めてまいります。そのなかで、新年度は、踊りの後継者育成として、踊りに関わりたい中高校生が参加しやすい環境づくりを進めていきます。例えば、午後10時以降に行う屋形曳きなどについては、岐阜県青少年健全育成条例を踏まえるなかで、踊り運営に関わる中高校生が安心安全に参加できる環境を整え、地域文化の発展に貢献できるようにします。
歴史文化の関連施設につきましては、市民の皆様からいただいた多様なご意見を踏まえ、郡上市歴史資料館・郡上八幡まちなみ交流館・郡上八幡町屋敷越前屋・大和古今伝授の里フィールドミュージアムの運営のあり方について、文化財の管理も含め、管理運営手法の見直しを行います。市民の皆様の理解を得られる形での施設の存続を目指し、維持管理費などが必要以上に財政面での大きな負担とならないよう、しっかりと検討しながら見直しを進めてまいります。
また、スポーツ振興においては、国が示す休日学校部活動の地域クラブ活動への段階的な移行に伴い、クラブ間の連携や統合による合同練習の実施などを加速し、学校部活動の地域クラブ活動への移行を完了します。
5.自治・まちづくり(市民と行政が協働でつくるまち)
次に、5つ目の柱である『自治・まちづくり』についてであります。
郡上市の未来を形作るためには、市民参画によるまちづくり、市民や議会との協働によるまちづくりを進めていくことが欠かせません。郡上市が誕生した際、合併前の旧町村議会の代わりとして地域審議会が設けられ、これが現在の地域協議会へ移行したものと認識しています。しかしながら、地域協議会の活動には温度差が見られ、そのあり方を見直す必要があると考えております。このために、先般の議会からのご提言を受けて、振興事務所長枠の予算を増額し、地域協議会を含めた地域での自治まちづくりを強化していきます。また、若者の参画を重視して、新たに「若者プロジェクト推進事業」を立ち上げます。これは、次世代を担う若者を育成し、彼らの柔軟な発想を取り入れながら持続可能なまちづくりを進めるものです。
男女共同参画については、国も推進している大切な取組みです。性別による無意識の思い込みや固定観念に縛られることなく、誰もが自分らしく活躍できるまちであることが郡上市の魅力を高め、ひいては消滅可能性都市からの脱却につながると考えています。そのために、第4次男女共同参画プランに基づく取組みを着実に進めていきます。男女共同参画社会の実現に向けて、市が旗を振るだけではなく、市民や多くの事業者、教育関係者の皆様もこの意識を持ち、環境づくりに努めていただきたいと思います。
郡上市は単独でのまちづくりにとどまらず、国内各都市との交流を通じて新たな考えを取り入れ、関係人口の創出を図らなければなりません。現在、協定を締結している東京都港区や志摩市とは様々な交流を進めていますが、郡上から移住された方々が多く住む北海道下川町とのつながりも強化し、若者が交流できる場を提供することで、新しいアイデアを郡上に持ち込んでまいります。
6.地域振興(個性あふれる地域づくりを推進するまち)
次に、6つ目の柱である『地域振興』における特徴的な取組みについて申し上げます。
和良地域において、濃飛横断自動車道の開通は、地域振興の大きな転機になると考えています。この道路の開通を見据え検討を進めている和良地域振興施設整備については、道路整備の進捗状況を勘案しつつ、県関係部署と情報共有を図るとともに、地域の皆様や市内外の関係者等からの意見を伺いながら、事業候補地における将来の用地取得を見据えた整備規模や動線の検討を行います。
さらに、中部縦貫道が白鳥町に延伸されることに伴い、白鳥地域の振興策も急務です。2年から3年後には、高規格道路により福井市と白鳥町が結ばれる予定であり、この道路を往来されるお客様にどうやって白鳥へ下りていただけるかが鍵となってきます。白鳥地域の皆様が地域をどのように発展させたいかをしっかりと伺い、市としても道の駅「清流の里しろとり」をはじめとする3つの道の駅の有効活用を中心に、地域の振興と発展を図っていきます。
7.行財政運営(健全な行財政運営を実行するまち)
最後に、7つ目の柱である『行財政運営』についてであります。
健全な行政運営のため、特にふるさと納税の活用に注力しています。この取組みは、市全体の財政基盤を支える重要な要素となっています。今年度のふるさと納税については、多くのご縁のある方々からのご支援を受け、昨年度と比較し1月末現在において合計で3,457万6千円の増収がありました。これは、市の財政を潤すだけでなく、市内事業者への返礼品支払いを通じて、地域経済の活性化にも寄与しています。新年度においては、専門のスキルを有する事業者の支援のもと、返礼品やポータルサイトの掲載内容等の充実を進めることで更なる寄附獲得を図ります。
職員の働き方改革、業務改善や経常経費の削減を目的に、これまで本庁舎や白鳥庁舎以外にも職員を配置し行ってきた宿日直業務は、夜間の電話や休日における戸籍の届出などの取扱い件数が極めて少ない状況等を踏まえ、宿直は本庁舎のみ、日直は本庁舎と白鳥庁舎の2つに集約します。また、本庁舎及び振興事務所の窓口業務については、今後のDXと併せ、書かない窓口の導入や、他の公的機関との連携も考えながらご不便が生じないよう進めていきます。
市有財産の活用についても重要な課題です。特に、市有林の立木販売や市有地の賃貸、さらに、統合後の旧学校施設の活用を進めてまいります。公共施設の適正な配置を進めるため、利用状況や老朽化の状態を踏まえつつ、所期の役割を果たした施設等については適切に見直してまいります。歴代市長が示された方向性に従い、市民の皆様のご理解を得ながら進めていく所存です。昨年の大和と高鷲の斎場の閉鎖により、年間180万円の維持管理費の削減が実現しました。このような小さな積み重ねが大きな成果につながることを、市民の皆様にはぜひご理解いただきたいと思います。
以上、令和7年度の予算編成に当たり、市政運営の基本的な考え方と予算編成方針、また、主要施策の概要について申し上げました。次の20年を見据え、持続可能な郡上市の未来に向けて市一丸となり取り組んでまいりたいと思いますので、議員の皆様並びに市民の皆様には、今後ともご支援とご協力をお願い申し上げます。
令和7年2月26日
| 郡上市長 | 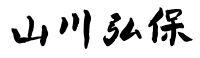 |