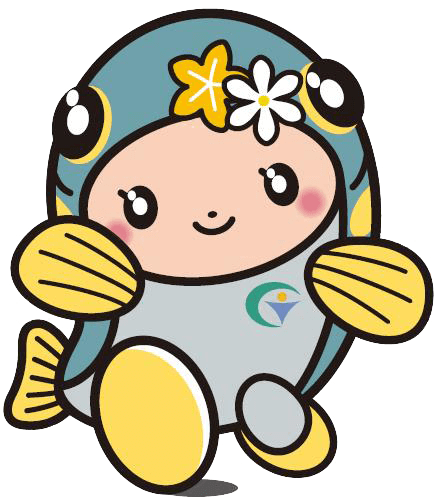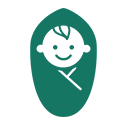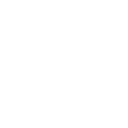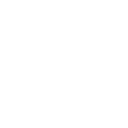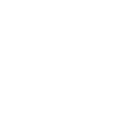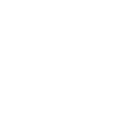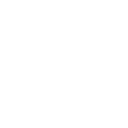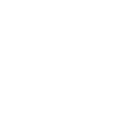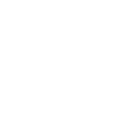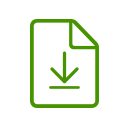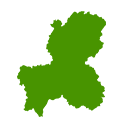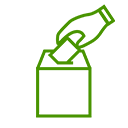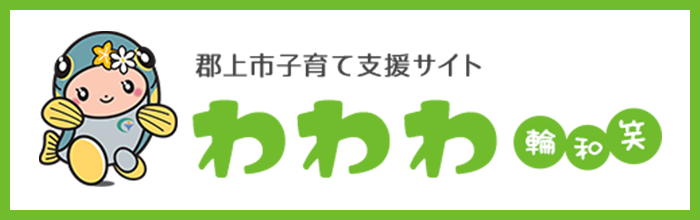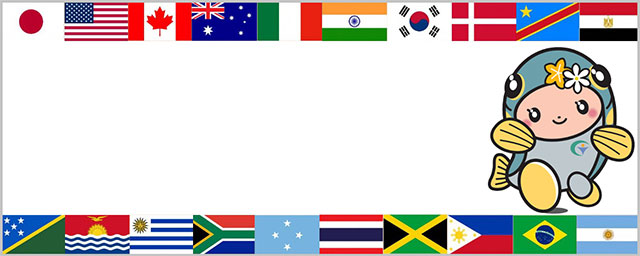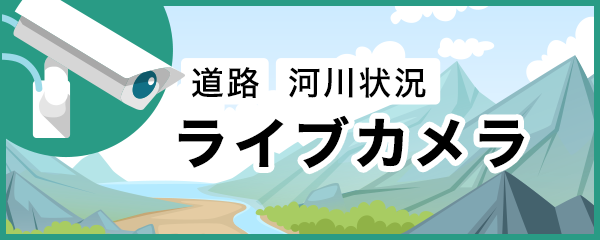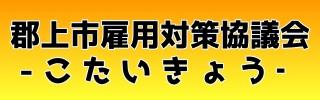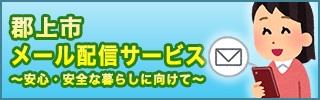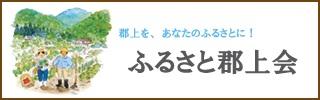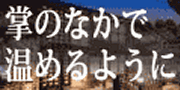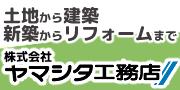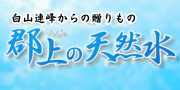八幡地域は「郡上八幡」と呼び親しまれ、四季を通じて観光地としての賑わいをみせる地域です。歴史も古く、郡上おどりをはじめとする様々な文化が発達した城下町を散策してください。

歴史
郡上の歴史は平安時代、武儀郡より分離独立し、郡内に四つの郷と、七座の神々が記録された頃より始まると考えられます。その後四郷が三つの荘園となり、中世に続きます。
中世は、坂東平氏の一族である郡上東氏(とうし)の興亡とともに推移しました。東氏は代々歌道の達人を輩出し、特に十代目にあたる東常縁(とうのつねより)は「古今和歌集」の権威として知られ、奥義を受けるため、都から訪れた連歌師宗祇(そうぎ)に対して、3年の歳月を経て「古今伝授」を行った事は歴史的な事でした。東氏はこれらの時代、現在の大和町にある、阿千葉城(あちばじょう)、篠脇城(しのわきじょう)、そして八幡町の赤谷山城と移り住み、外敵とも戦いました。しかし永禄二年(1559年)遠藤盛数(えんどうもりかず)により落城し、盛数は現在の八幡城を築きました。その子慶隆(よしたか)らによって八幡城下は整えられて来ました。1588年遠藤氏が秀吉によって左遷され、稲葉貞道が郡上を治めます。
関ヶ原の合戦の後、家康により、稲葉氏は大分県臼杵へ転封され、再び遠藤慶隆が治める事となります。江戸時代に入り、郡上は、遠藤氏の後、井上氏、金森氏、青山氏と続いて、明治を迎える事になります。東京都港区の「青山」なる地名は、青山氏の下屋敷があったことからついています。毎年6月には「郡上おどりin青山」が開催されています。
「郡上おどり」の発祥は、豊臣秀吉による朝鮮戦役の頃と考えられ、400年以上の歴史が刻まれています。
明治に入り廃藩置県と共に、八幡町は1町23村で構成され、同30年、合併が進み、1町5村となりました。昭和29年に、八幡町、川合村、相生村、口明方村、西和良村が合併し、同32年有坂村が編入され、現在の八幡地域になりました。