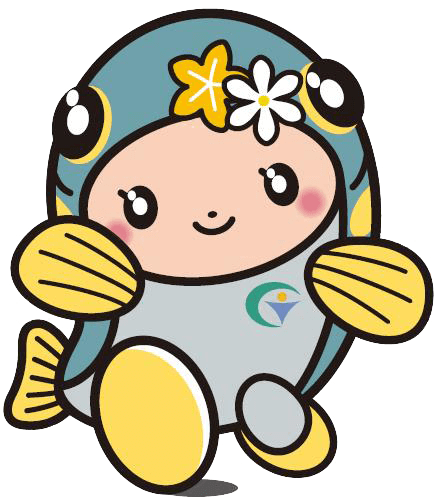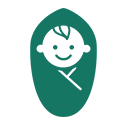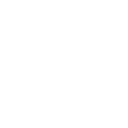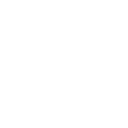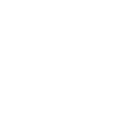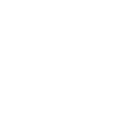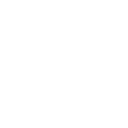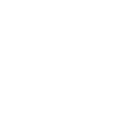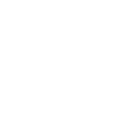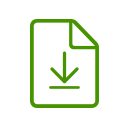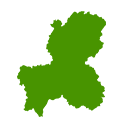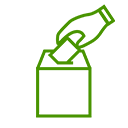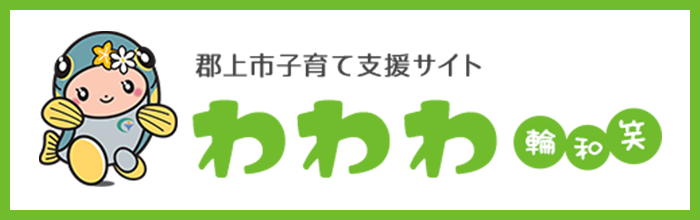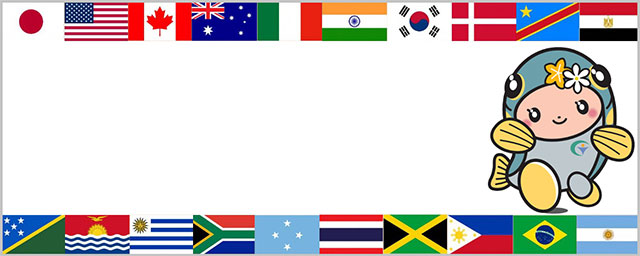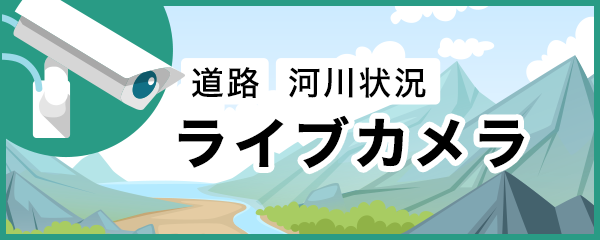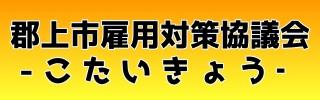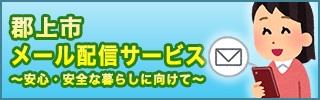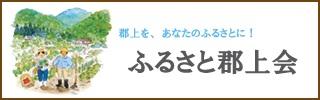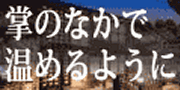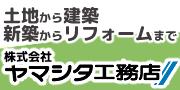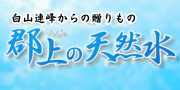美並地域は、奥長良川県立自然公園の一部を形成する長良川を有し、夏には鮎の友釣りで太公望が集い、ラフティングやカヌーで自然体験が満喫できます。うなぎを神様の使いと崇める粥川の森では森林浴が楽しめます。

はじめに
美並地域は奥長良川県立自然公園の一部を形成する長良川を有し、夏には鮎の友釣りを楽しむ人々で賑わいます。秋にはヤナ場で落ち鮎を味わうことができます。
粥川の森では百年杉の森や遊歩道が整備され自然とのふれあいを満喫することができます。
歴史
美並地域が歴史上姿を現すのは斉衡2年(855年)です。古代中世にわたって星の宮神社を中心にして山岳信仰が広がり、村の各地に白山神社がまつられることになりました。
一方、長良川を利用した、いかだ流しが古くから高原地区を中心に行なわれ、郡上の木材を集め、美濃地方への搬送は、昭和の初め頃でも、1700乗あったと言われています。陸路では、馬による人や荷物の輸送にあたる馬子制度が充実していました。
明治2年6月廃藩置県により、郡上藩は郡上県と笠松県となり、同4年11月に岐阜県となって、郡上県もその管轄となりました。
美並村においては、明治8年1月に合併して7箇村となり、更に明治22年3箇村が合併して嵩田村となり、他の4箇村は組合役場を白山村に置き、のちに合併して下川村となりました。
昭和29年11月1日、下川村と嵩田村が合併して、郡上の"みなみ"にあって、美しく並ぶ村とし「美並村」が誕生しました。