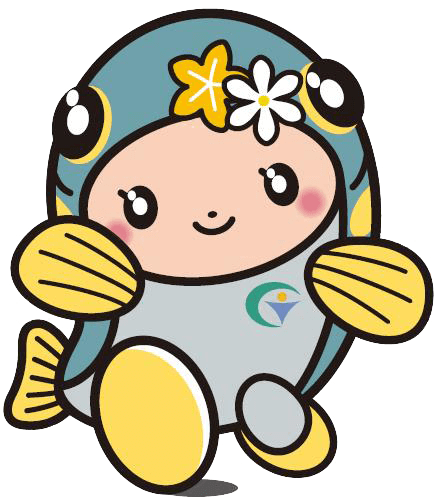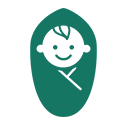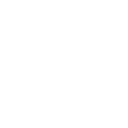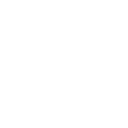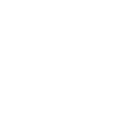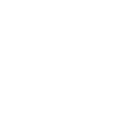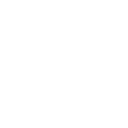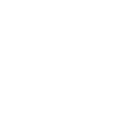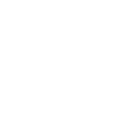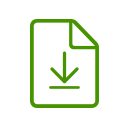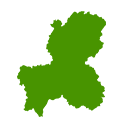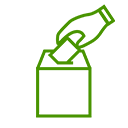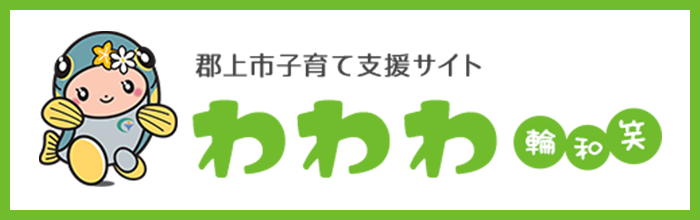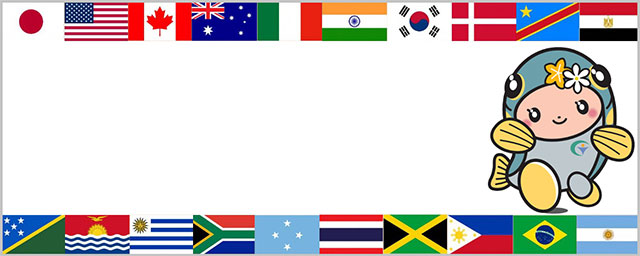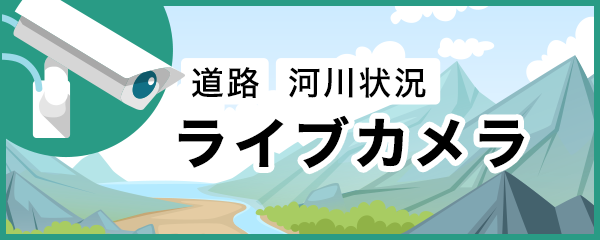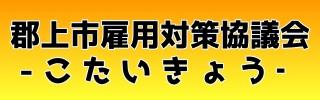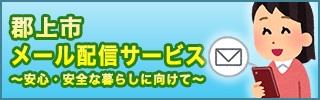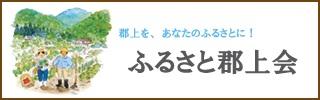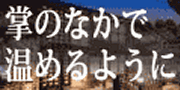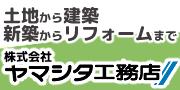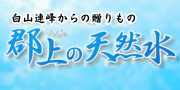大和地域は「古今伝授の里」。古今伝授(こきんでんじゅ)とは、古今和歌集の奥義を授けることで、中世の郡上の領主であった東常縁が確立しました。東氏の拠点であったこの地域には数々の遺跡が残っており、古今伝授の里フィールドミュージアムが開設されて、年間を通じ多彩なイベントが催されています。

歴史
大和町の歴史は古く、縄文時代をはじめ多くの遺跡や遺物が町内各地で発見されており、6世紀頃すでに大和朝廷とつながりを持つ豪族がいたと考えられます。
中世にはいると、承久の乱(1221年)の戦功によって、下総の国より東氏が入部し、約340年間にわたり郡上を統治しました。東氏は代々武家の歌人として有名で、郡上東氏初代・胤行は、藤原為家に師事しその娘を妻にしたと伝えられます。九代・常縁は、連歌師・宗祇に古今伝授を行ってこれを確立し、「古今伝授の祖」と言われました。また、応仁の乱で東氏の居城であった篠脇城が落とされますが、常縁は十首の和歌を詠んで相手方に贈り、無血のうちに城が返還されたという有名な故事があります。その後、東氏は越前朝倉氏の来襲を機に、篠脇城を廃城にして拠点を郡上八幡に移すことになりました。
1979年、篠脇城の麓に東氏の館跡が見つかり、ほぼ原型に近い庭園遺構が発掘されました。庭園は、美しい石組みと当時の武将の生活をしのばせる高い学術的価値により、1987年、岐阜県下では3箇所目の国の名勝に指定されました。さらに2006年には国の史跡にも指定されました。