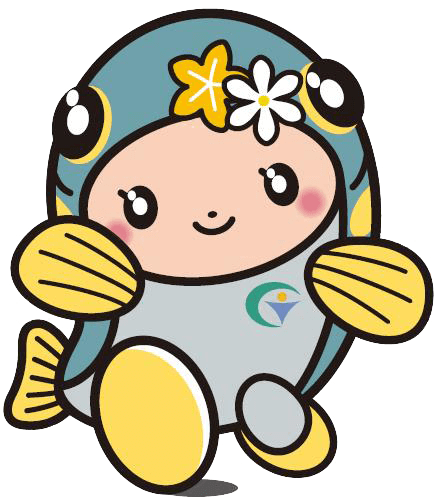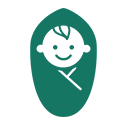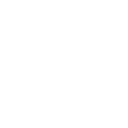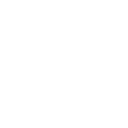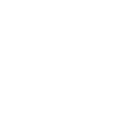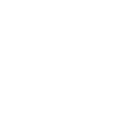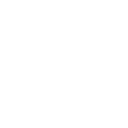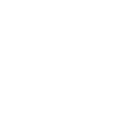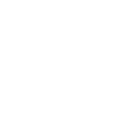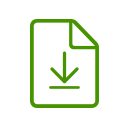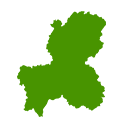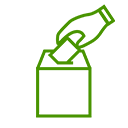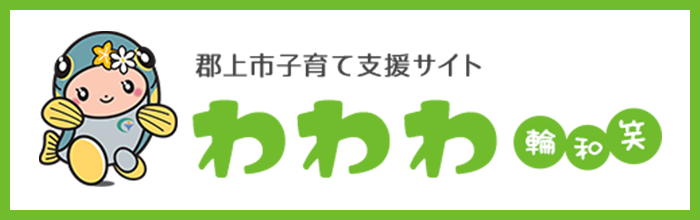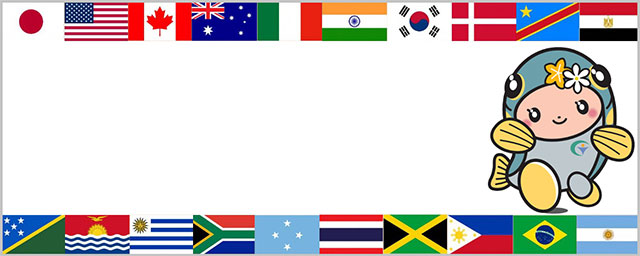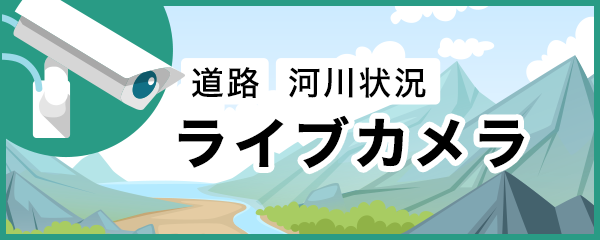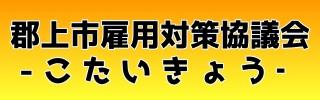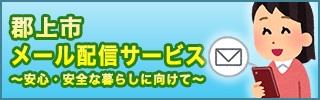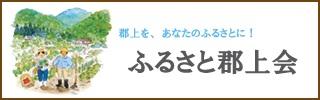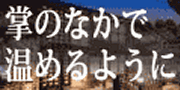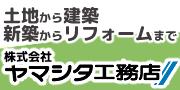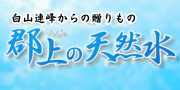新春 歌合わせ会(2月初旬)
平安時代に生まれた"歌合わせ会"を、現代の大和流ルールで行います。お題に添って出された歌を紅白に分けて、その優劣を判定する文学的なゲームです。
【古今伝授の里フィールドミュージアム】
母袋ひなまつり(4月初旬)
地域の方から持ち寄られた1,700体のひな人形や代々伝わる土雛・土人形が飾られ、子供の健やかな成長を願ってお祝いします。
【上栗巣体育館】

明建神社の桜並木(4月中旬)
明建神社の横参道には約250mにわたって100本あまりのヤマザクラやソメイヨシノがならび、4月中旬に桜のトンネルとなります。
【牧:妙見集落】
ゆきばた椿まつり(4月下旬)
「ヤブツバキ」と「ユキツバキ」の自然交雑による「ユキバタツバキ」の素晴らしさを知っていただくとともに、自生地の保護を目的に開催されます。自生地見学会、椿や椿作品(書・絵・布)展示、椿グッズの販売、マルシェなどが行われます。
【古今伝授の里フィールドミュージアム・大間見周戸】
ぼたんまつり(5月初旬)
古今伝授の里フィールドミュージアムにある"ぼたん園"では2,000m2に約10種類の品種1,000株のぼたんを無料で鑑賞でき、例年はゴールデンウィーク後半に一斉に咲き誇ります。
【古今伝授の里フィールドミュージアム:ぼたん園】
薪能「くるす桜」(8月7日)
明建神社で上演される薪能(野外公演)。 中世に当地を治めた「東 常縁」を題材にしたオリジナル薪能『くるす桜』が上演されます。薪の炎に照らし出された舞は、観客を幽玄の世界へと誘います。【牧:明建神社】
郡上長良川夢花火(8月中旬)
願い事、夢や思い、大切な人へのメッセージをのせて、千発以上の花火が大和の夜空いっぱいに打ち上げられます。
【奥長良ウィンドパーク】
第40回やまとふれあい祭りファイナル(10月18日)
地域の人たちが集い楽しむ秋の恒例行事。 舞台発表、作品展示、各種体験、景品付きアメ投げ、フリーマーケット、バザー等、楽しい催しが行われます。
【郡上市役所大和庁舎】
古今伝授の里やまと どぶろくまつり(10月下旬)
大和エリアが「どぶろく特区」となったのを機にはじめられたイベント。やまとふれあい祭りで、母袋工房「奥の奥」、三河屋「大和歌魅」、リゾートペンション四季彩「水沢上ヶ池」それぞれのどぶろくが振る舞われます。
【郡上市役所大和庁舎】