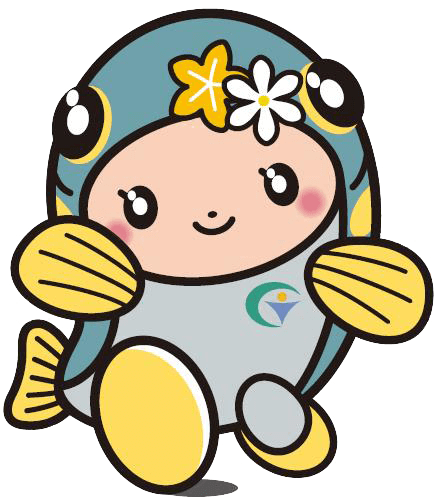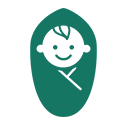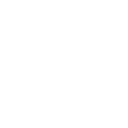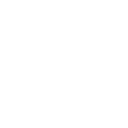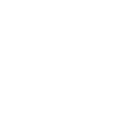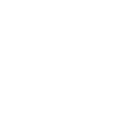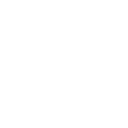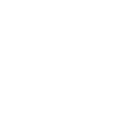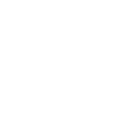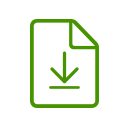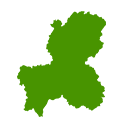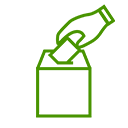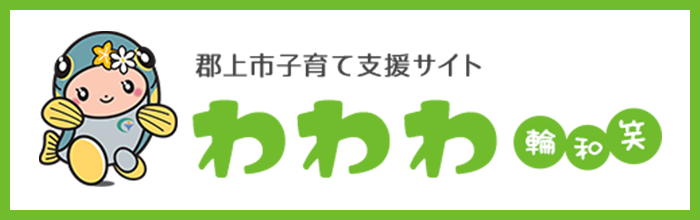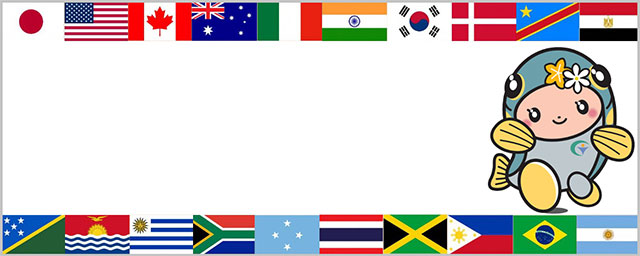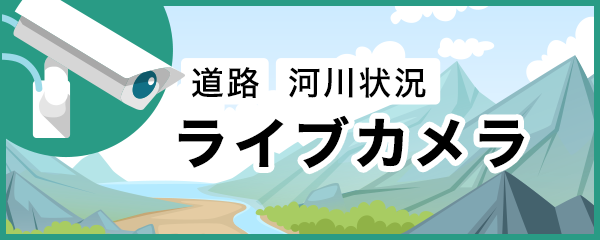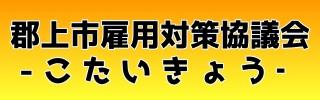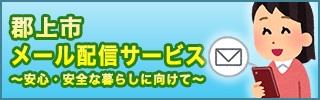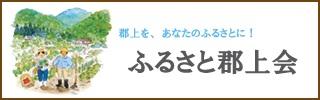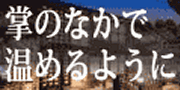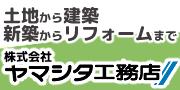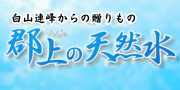指針を策定した背景
郡上市では、平成17年度に郡上市総合計画を策定し、「みんなでつくる郡上」をまちづくりの基本理念に掲げ、「自立・自律」、「協働と補完」を基本方針としました。これは、市民に身近な課題は市民自らが解決への取り組みを行い(自立・自律)、その範囲を超える課題については、行政が取り組む(補完)とする考え方です。平成19年11月には、「郡上市まちづくり市民会議」を立ち上げ、市民協働について、多くの議論を重ねてきました。平成21年1月30日に郡上市まちづくり市民会議から市長へ「郡上市市民協働指針(案)」を提言いただきました。 この指針案を成案化するため、パブリックコメント制度を活用しながら、多くの市民の意見を取り入れ今回「郡上市市民協働指針」として策定しました。
指針の内容
「郡上市市民協働指針」は、第1章から第9章で構成され、市民協働のあり方、市民協働を進めるための役割と責任、市民協働を進める環境づくりなど、市民協働を推進するための進むべき方向が示されています。
協働のあり方や協働を進めるための役割と責任とは
市民協働を円滑に進めていくには、基本原則やルールをきめておくことが大切です。市民個人、地域団体、市民団体、NPO法人、事業者、行政のそれぞれが果たす役割や、協働の領域とはどのようなものか、また、市民協働の形にはどのようなものがあるのかを明らかにしておく必要があります。
市民協働を具体的に考えると
市民協働についての大まかな流れを、イメージすることで協働を進めやすくなります。市民協働を進めていく際には、一気に進めないで、段階を追って多くの人の意見を取り入れながら整理していきます。
市民協働を進める環境づくりについて
市民協働を進める上では、課題の共有を図ることが大切です。そのためには、まず、情報を共有することやその情報を提供する仕組み、情報を得るための市民の姿勢、さらには意見交換の場が必要となります。また、市民協働の考えを理解する人を増やすための、人材育成が必要です。
市民協働センターについて
市民協働を進めるためには「市民」と「行政」を対等な立場で調整する組織が必要です。市民協働は、市民と行政がパートナーとなって、ひとつの目的に向かい、力を合わせて努力していく活動です。対等な立場で活動を進めるためには、その間に立って支援し調整する第三者機関として中立の立場で市民協働を進める機関が求められます。
市民協働の検証と見直しについて
協働により取り組んだ課題については、その効果を常に検証していくことが必要です。上手く課題の解決が進まない場合はいつでも話し合って取り組み方を変えていくなど検証結果を柔軟に次の活動に反映させていくことが大切です。また、この指針についても修正が必要になれば柔軟に見直す姿勢が必要です。
市民協働の事例について
市民協働を具体的に理解するために、いくつかの事例を示しています。